イベント情報を読み込み中...

どんな会社でもできる インナー・ブランディングセミナー (オンデマンド視聴)
イベント概要
2023.11.15に開催した新刊刊行記念、
「どんな会社でもできるインナーブランディング・セミナー」を
録画したものです。
お申し込みのみなさまにURLを配信いたします。
インナー・ブランディングとは、「ブランドの理論を土台にした効率的な組織づくり」を実施することです。どんな課題に効き、どう具体的に行っていくのかを、本書に沿ってダイジェスト解説いたします。
<こんな悩みを持つ経営者・責任者の方向け>
組織の方向が揃わない。みんなバラバラ。
創業メンバー、中途、新卒入社が混在でカオス。
入社してもすぐに辞める。
人が育たない。
従業員の文句や愚痴が多い。
お金をかけているはずなのに採用できない。
なんとなく流れに沿って成長してきてしまった。
自分たちなりの成功法則がまだ見いだせていない。
登壇者
深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランスで5度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても”光る人材”が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。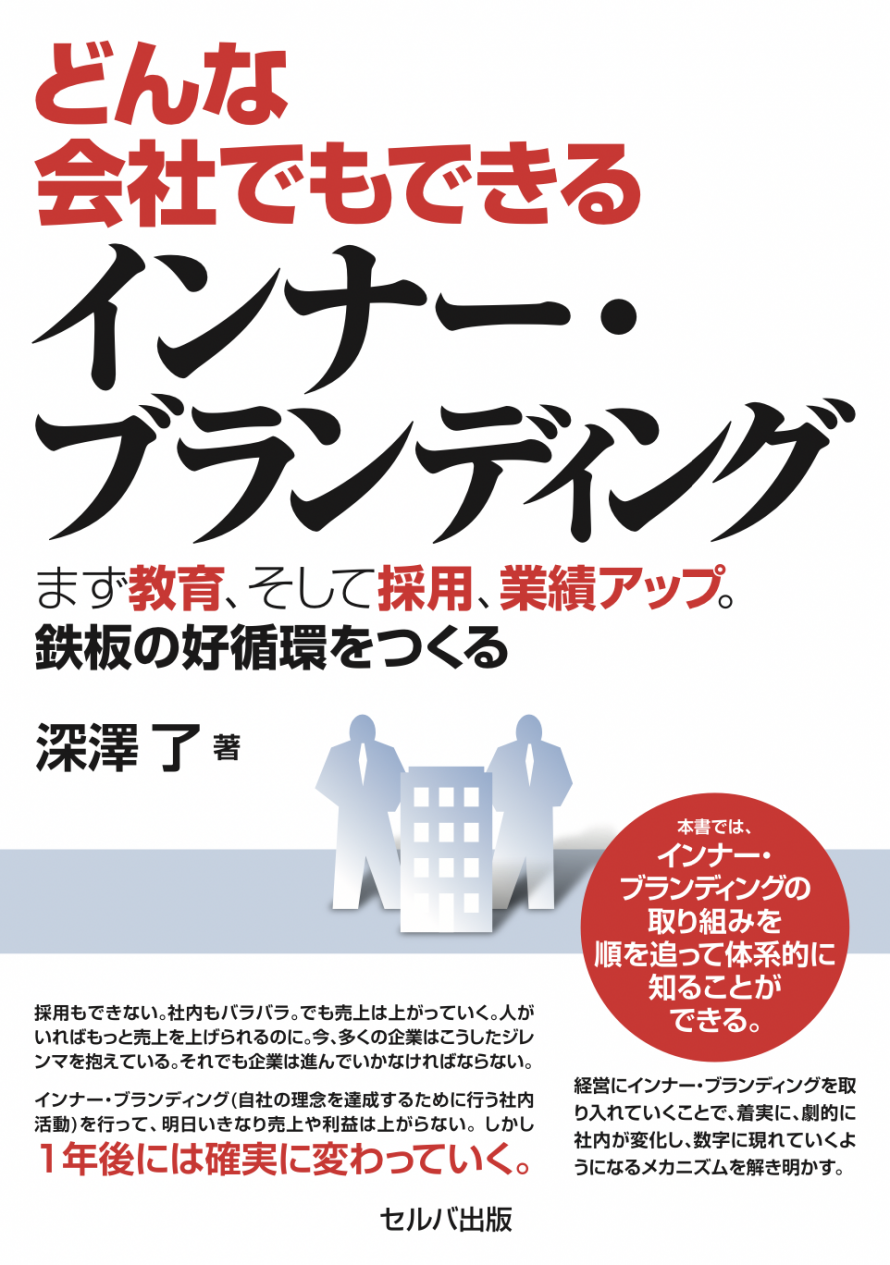
アマゾンで注文したい方はこちら(遷移します)
https://amzn.asia/d/30EWqzR
<もくじ>
はじめに 真の競争力をつくるインナー・ブランディング
第1章 なぜ優秀な人材ほど退職するのか。間違いだらけの採用と育成。
1,35年変わらない入社3年で離職率3割。
2,茶番化している採用構造。
3,さらにミスマッチを誘発しやすい採用市場の構造。
4,母集団集めばかりに走るから採用できない。
5,能力で採用する罠。
6,担当任せの採用が失敗を導く。
7,面接官任せの採用がミスマッチを招く。
8,採用と教育が連動していない企業がほとんど。
9,会社の向かう先と個人の向かう先の不一致。
10,人はカルチャーマッチしてこそ活躍できる。
第2章 差別化を生み出すインナー・ブランディングの取り組み
1,ブランドでいちばん大事なことは一貫性。
2,浸透には段階がある。
3,理念を言語化する。
4,つくるところから浸透は始まっている。
5,10段階あるプロジェクトの工程
6,大々的に社内に伝える。周到に準備する。
7,浸透は、定量と定性でチェックする。
8,社内に理念、教育、制度、しくみ、すべてを連動して強い文化をつくる。
9,採用ブランディングがインナー・ブランディングの始まり。
10,サスティナブルを踏まえ、強みにする。
第3章 インナー・ブランディングを成功させるための採用
1,ザル採用、ザル浸透にしないために、採用から始める。
2,徹底的に強みで勝負する。
3,なぜ弱みを整理しなければならないのか。
4,スキルや能力ではなく、譲れない価値観を明確にする。
5,ペルソナは超理想を描け。
6,採用活動はコンセプトが肝。
7,制作物だけで採用課題は解決できない。
8,ほとんどの人は知らない、制作物の役割。
9,圧倒的差別化を生む採用フロー。
10,採用して教育を始めない。教育は母集団形成から始まっている。
第4章 売れ続ける組織をつくるインナー・ブランディングによる効果
1,戦略づくりと組織づくりの一石二鳥。
2,ここにいるべき人だけが残る。
3,教育とマネジメントがしやすくなる。
4,採用で差別化できる。採用力が上がる。採用単価が落ちる。
5,採用がマーケティングの場になる。
6,理念で集まる組織づくり。
7,抜群の投資対効果。
8,売上を上げ続けるしくみができる。
第5章 インナー・ブランディングの取り組み事例
1,事例1 株式会社ギフト
2,事例2 株式会社大庄
3,事例3 株式会社ユーニック・株式会社トーセン
4,事例4 日本テレネット株式会社
第6章 インナー・ブランディングの成功ポイント&失敗ポイント。
1,何のためにインナー・ブランディングを行うのか常に確認する。
2,社長が必ずコミットする。
3,社内における優先順位を第一位にする。
4,一人ひとりに期待を伝える。
5,付箋でやれば、声の大きな人の意見に引っ張られない。
6,アイデアの質ではなく、量を競い合う。
7,意見を否定しない。意見を出したことを承認する。
8,社長がひっくり返さない。
9,決めたこと、取り組み内容を協力会社にレクチャーする。
10,実行し続ける。1ミリでも前に進める。
第7章 定着、活躍、成長する会社へのステップ。〜社内浸透&マネジメントの要点
1,川上から川下へ。社長→役員→部課長→従業員の順番でしか浸透は進まない。
2,朝礼、会議など定例の時間を利用する。
3,会社の方向性と、個人のやり甲斐を一致させる。
4,10分でOK。毎週、個人面談の時間をとる。
5,理念に沿って行動し、結果を出している人を最も評価する。
6,結果を出している人同士で刺激し合う場をつくる。
7,反発・抵抗する人とは徹底的に話し合う。
8,辞めていく人が出ることを覚悟する。
あとがき
参考文献
イベント詳細
イベントに参加する
ログインすると外部サイトで登録できます
CXO交流会カレンダーは、役員以上(CEO、CFO、COO、CTO、CMO、CHROなど)限定のサービスです。

自分で考え動くチームへ!離職率も指示待ちのムダも同時に下げる「自律型組織」構築セミナー

「つくる会計」の日本企業が目指すべき、グローバル標準の「つかう会計」とは

【経営者限定】 株式会社クロス・マーケティングCEO五十嵐様ご登壇!! | EO Nagoya 2026年1月例会

【受講生の70%が経営者・役員】仕組み化や事業拡大に悩む経営者・役員のための事業戦略スクール「知足(ちそく)」説明会

【無料/経営者・ビジネスリーダー向け】 生産性を高める集中力リセット体験(45分) ― 福利厚生ではない「仕事の質を整える企業ヨガ」―
